こだわりのさぬきうどん お取り寄せ 贈答・進物にも 日の出製麺所(四国 香川 坂出)
![]()
さぬきうどん職人ニューヨークへ行く!(本番編)
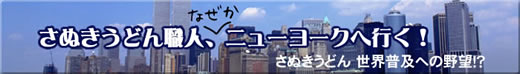
四国香川の名産「さぬきうどん」を世界へ・・・と。
「SANUKIプロジェクト」というものが有志でこの5月に立ち上がり、現地在住のさぬき出身者(ニューヨーク香川県人会)より声をかけてもらい海を渡りました。
◆SANUKIプロジェクトとは・・・・・
ニューヨークをはじめ「カラオケ」「スシ」は世界共通語になっておりますがうどんも世界共通語になるくらい、また、うどんを「サヌキ」と呼んでもらえるくらいに世界に広めたいと言う「さぬきおこし」的な私設団体。
ニューヨーク在住で香川県出身の27歳〜28歳の幼なじみ(伊藤、大坂、三好)3人組が発端で結成されどんどん渦が大きくなり、うどんの部門で声をかけて頂き今回の試みとなりました。
前回は「出発・到着編」として第1弾をお知らせいたしました。第1弾はこちらからご覧いただけます。
そして、いよいよさぬきうどんのお披露目のときがやってきました!
いよいよ撮影当日
 ▲本番前の打合せ…何話してるかわかりません…(汗) |
平日なので仕事を抜け出してくるメンバーもおります。
そうです彼らも「さぬきプロジェクト」に見返りを求めず、交通費から通信費、ちょっとした食材費、諸経費を全て自費で捻出しボランティアに参加し「さぬき」をNYで誰もが知ってる言葉にしたいという思いだけで動いております。
それに感動して今回、海を渡りました。
いよいよスタジオ入り・・・
言葉が通じない、もちろん番組は英語、打ち合わせは英語、私は英検3級・・(^_^;)
メンバーだけの時は日本語なのですが、放送局のスタッフ、カメラマン、プロデューサーと打ち合わせはさっぱりわかりません。
とりあえず17分で粉からうどんを練って伸ばして切って茹でて食べるということらしい。
う〜〜ん?
ということは練った物と団子にしたものと茹でて出来上がったものを用意しとかなければ…
スタジオに着くなり大忙しで湯を沸かし、うどんを先に打ち茹で出来上がりのものを先に造り置きし準備完了です。
そして本番・・・・!!!
 ▲本番中の光景! |
はじめにメンバーの紹介があり合図があってからうどんを作っていきます。
もう17分という時間は全く私の頭にありません。
何を言っているのかはわかりませんがスタジオは盛り上がっています。
調子よくうどんを切っているとなにやらスタッフが私に合図を送っています。
スタッフの手がメチャメチャ早く回ってます。
だんだん顔が怖くなってきました。
あまり意味がわかりませんでしたがおそらく急げということだろうと思い素早く切ってしまい、そこからは先に作った出来上がっているうどんをだして無事終了いたしましたが。
本来、司会者のジャナックさんに食べてもらうところまでもって行きたかったのに時間切れになってしまったことが残念です。
しかし、無事に収録が終わりほっとしました。
そのあとにスタッフの方々と握手し御礼を言ってスタジオをあとにしました。
驚いたのが女性プロデューサーさんに御礼とお別れを言ったあとに握手し抱擁があったことです。(さすがアメリカ!)帰りのタクシーの中ではメンバーもみんな緊張から解き放たれて「抜け殻」気味になっていました。
夜も日本食レストランでうどん打ち!
夜は「鬼が島」という日本食(そば、うどん専門店)レストランでニューヨークの人たちをターゲットにしたイベントを行うということで、休む間なく早速準備にとりかかりました。
ここでもやはり手打ちうどんの実演をし、お客様(約50名)の方々に試食してもらいながらパーティーをするという日本でもよくやっているうどん打ち会みたいな形式です。
確かに多くの方が来てくれました。
どっちかというと日本びいきの日本食通みたいな外人さんばかりで、うどんの味などわからないだろうと油断していた私は一瞬ひるみましたがここで「ええもん」だして認めささないかん!
讃岐(香川県)から来とる限りはNYの日本食レストラン、そば屋、うどん屋で食べたことないうどんを出さないかん!と、日ごろおとなしい私が熱くなったのが自分でわかりました。
また 、彼らはNYの日本レストランを結構、制覇しているので本当に口がこえているのには驚きました。
NYの日本食は結構レベル高いです。値段は日本より少々高めですがネタとか味は日本との差はたいしてありません。
”さぬきうどん職人”として充実感を味わう!
たくさんのお客さんが入りみんなこっちを見ています。
とりあえずデモンストレーションを軽く終えお客さんにも少しうどん打ちをしてもらい言葉は通じませんが心は通じ合ったように思います。
金髪の青い目をしたアメリカ人、ヨーロッパ人、全身刺青の中国人、インド人、台湾人の人たちが本当に楽しそうにうどんを打っているのを見て「やっぱり来てよかった」と実感しました。
そして出来上がったうどんをみんなおいしいと言ってくれたのがうれしくて舞い上がってしまいました。
私もNYでここまでのうどんが作れると思えないほどおいしいうどんができました。
ほんで、香川県出身者もそこにいたのですが「まさか、ニューヨークでこんなうどんが食べれるとは思ってなかった」とか「あそこの○○うどんの味に似とる!なつかしいわ!」とか
「こんなん絶対こっちでは食べられへん!今日、来てよかった!」
私にとってはこれ以上ない誉め言葉をくれたのです。
そこで思いました。
「そうかこの人たちが喜んでくれただけでも私にとっては大成功かな・・・・。」
「ニューヨークの人たちもそうだけど、まずニューヨークにいる日本人に喜んでもらわないと、
さぬきの人に認めてもらわないとうどんは認めてもらえないだろう・・・。」
今回のニューヨークで最大の意義がこのイベントを通じて自分自身に沁みました。
そうこうしながらあっという間のNYでしたがとても濃厚な濃い3日間でした。
そして、帰ってきて思ったのは、まず、足元からなんだと土台を担ってくれる人たちに集まってもらわなければ・・・。
ニューヨークの「さぬきプロジェクト」のメンバーもそうだけど日本の人たちや「さぬき」の人たちの力によって成り立っていくプロジェクトだと思いました。
そして、先日ですがメンバーの伊藤智子(代表)が帰国して(なんと香川県での滞在時間10時間弱)県知事に直接お会いしまた、Tさん(今回のうどんブームの仕掛け人)、四国新聞社さんにも表敬訪問し熱く思いを伝えたということです。
恐るべき行動力!(しかも自己負担)
本当に彼らの「讃岐」を思う気持ちには敬服いたします。
私もこっちで(香川県)で何ができるかを常に考えて「讃岐」のために何かしていかなければと思います。
これからも皆様のご支援ご指導こそが我々のこれからの道しるべでありますので何卒宜しくお願い致します。
